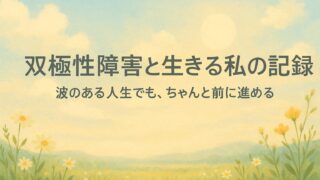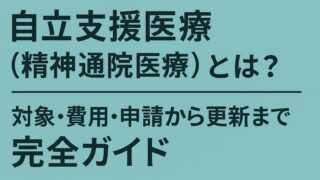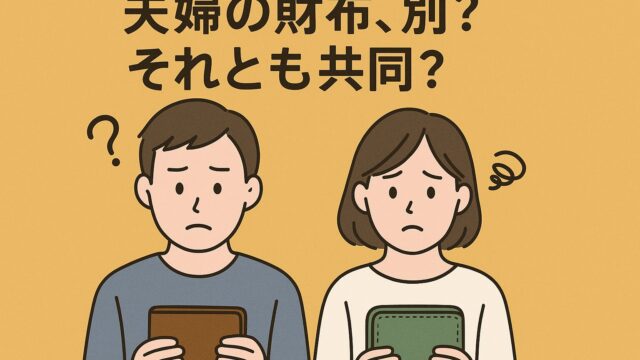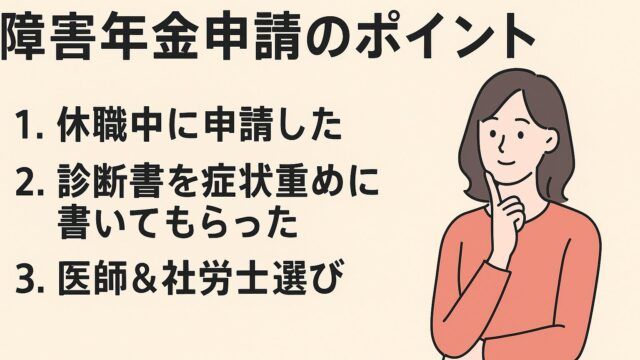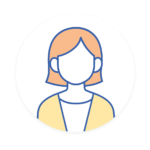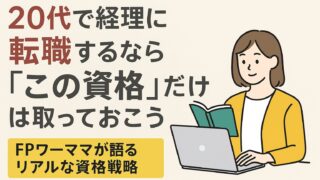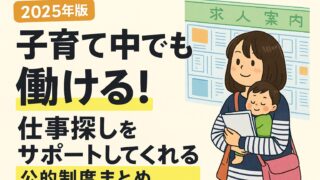🕊️父親の虐待を乗り越えて——26年かけて「許す」ことができた私の話

- はじめに:なぜ今、父のことを書こうと思ったのか
- 幼少期——3歳で経験した「最初の恐怖」
- 家という密室——優しい父の裏の顔
- 助けてくれなかった大人たち
- 勉強が唯一の逃げ道だった
- 母との関係:もうひとつの孤独
- 親友の涙がくれた“人間としての救い”
- 上京——逃げるように離れた家
- 第8章 自由のはずだった東京生活と、夜のフラッシュバック
- 第9章 心の病との出会い——双極性障害という現実
- 第10章 「理解すること」と「許すこと」は違う
- 第11章 YouTubeが与えた転機——“許す”というテーマ
- 第12章 父との再会:沈黙の車中で
- 第13章 「ゆき、あの時はごめんな」——30年分の涙
- 第14章 許すことの意味——自分を自由にする選択
- 第15章 距離を保つという新しい関係性
- 第16章 母への気持ち、そして妹との絆
- 第17章 私が親になって気づいたこと
- 第18章 過去の自分への手紙
- 第19章 おわりに:同じように苦しむ人へ伝えたいこと
- 結び
はじめに:なぜ今、父のことを書こうと思ったのか
父のことを書くのは、これが初めてではない。
日記のようなメモには、何度も書いてきた。
「憎い」「もう関わりたくない」「私の人生を壊した人」――
そうした言葉を残してきた。
けれど、時を経て、ようやく気づいた。
怒りや悲しみを書くだけでは、心は軽くならない。
今年になって、父と再び会った。
その瞬間、26年間抱えてきた感情が、ひとつずつ形を変えていくのを感じた。
「許す」という言葉の意味を、私は初めて理解した気がした。
だから今、記録として、そして誰かの助けになればと思いながら、この文章を書いている。
これは“美談”ではない。
一人の娘として、暴力の連鎖をどう断ち切ったかという現実の記録である。
幼少期——3歳で経験した「最初の恐怖」
私の記憶の中で、最も古い「恐怖」は、三歳のときに始まった。
その日は何でもない日だった。
父に「お風呂に入りなさい」と呼ばれたのに、私は遊びに夢中で聞こえなかった。
次の瞬間、怒鳴り声とともに腕をつかまれ、真っ暗な押し入れに閉じ込められた。
暗闇の中で息を潜めると、畳の匂いと古い布団の湿った臭いが鼻に刺さった。
時間の感覚はなく、どのくらい閉じ込められていたのか覚えていない。
ただ、「ごめんなさい」「もうしません」と何度も泣きながら叫んだ。
けれど誰も来なかった。
あのときの孤独感は、今も心の底に沈んでいる。
その瞬間、世界は「安全な場所ではない」と刷り込まれたのだと思う。
家という密室——優しい父の裏の顔
父は外では評判の良い人だった。
困っている人を助け、地域でも「優しい人」として知られていた。
しかし、家の中ではまるで別人のようになった。
怒り出すきっかけは、いつも些細なことだった。
箸の持ち方、返事のタイミング、洗面台の水滴。
声のトーンが低くなり、目つきが変わる。
その“予兆”を感じるたび、体が勝手に固まった。
家の中では、常に緊張していた。
父の機嫌次第で、一日の空気が変わる。
怒鳴り声のあとに訪れる沈黙が、何よりも怖かった。
助けてくれなかった大人たち
虐待の現場を知っていた大人は、実は何人もいた。
祖父母は同じ家に住んでいたし、母もその場にいた。
それでも、誰も止めなかった。
祖父母は「お父さんも疲れてるんだよ」「誰にも言っちゃだめだよ」と言った。
母は何も言わず、テレビを見ていた。
その背中を見ながら、私は「自分は守られない存在なのだ」と理解した。
「母はなぜ何も言わなかったのか」
この問いは、今でも心に残っている。
母は父より6歳年下で、経済的にも精神的にも父に依存していた。
それが“何も言えなかった理由”だと今なら理解できる。
だが、子どもの私には、ただの「裏切り」にしか感じられなかった。
勉強が唯一の逃げ道だった
小学校に入ってから、私は一つのルールを学んだ。
「成績が良ければ、父は怒らない」。
それが唯一の“防衛策”だった。
勉強は苦ではなかった。
むしろ「点数で身を守れる」という感覚があった。
だから必死に勉強した。
テストの結果が貼り出されると、私は順位表の上のほうに名前があるかを確認して、ようやく一息つけた。
中学では常にトップ5、高校は県内トップ3の進学校、そして大学は明治大学に進んだ。
だが、どんなに成果を出しても、父の態度が劇的に変わることはなかった。
私の努力は、ただ「次に怒られないための点数」でしかなかった。
母との関係:もうひとつの孤独
父の暴力よりも、母の無関心のほうが、後を引いたかもしれない。
母はいつも妹をかわいがり、私は「存在していない子ども」のように扱われた。
父に叩かれても、母はその横でテレビを見ていた。
「見て見ぬふり」という言葉の意味を、幼い私はその時に覚えた。
母の愛情を求めることを、いつの間にか諦めていた。
「どうせ自分なんて」という感覚は、その後の人間関係にも影を落とした。
親友の涙がくれた“人間としての救い”
中学のとき、一度だけ家のことを親友に話したことがある。
そのとき、彼女は何も言わず、ただ泣いた。
「そんなことがあったの?」と。
彼女の涙を見たとき、初めて「自分は悪くなかった」と思えた。
その夜、布団の中で泣いた。
でも、その涙は痛みではなく、安堵だった。
“私を理解してくれる人がいる”――それが、初めて感じた人間の温かさだった。
上京——逃げるように離れた家
大学進学で東京に出たとき、心の中は「自由」と「恐怖」で揺れていた。
家を出ることは、父からの解放を意味したが、同時に「家族を裏切るような罪悪感」もあった。
初めて一人暮らしをした夜、静かな部屋で泣いた。
「もう戻らなくていい」という安心感と、「これからは自分で生きるしかない」という緊張。
それでも、あの夜ほど“呼吸ができる”と感じた日はなかった。
家を出てから、長年の頭痛が消えた。
だが、心はまだ自由ではなかった。
第8章 自由のはずだった東京生活と、夜のフラッシュバック
東京での生活は、想像していた以上に静かだった。
父の怒鳴り声も、物が壊れる音もしない。
自分のペースで食事をし、好きな時間に眠ることができた。
ただそれだけのことが、信じられないほどの幸せに感じた。
だが、夜になると、過去が忍び寄ってきた。
夢の中で、幼い自分が押し入れの中で泣いている。
「ママ、助けて!」
その声で目が覚めると、汗でシーツが濡れていた。
フラッシュバックという言葉を、その頃の私は知らなかった。
けれど、あの夢が私の中に残っていた“恐怖の記憶”だと気づくまでに、それほど時間はかからなかった。
日中は明るく笑って過ごしていても、
夜は過去が追いかけてくる。
そんな生活が数年続いた。
そして、心が限界に近づいていたことに、自分でも気づいていなかった。
第9章 心の病との出会い——双極性障害という現実
社会人になって間もなく、情緒が不安定になった。
仕事に集中できない日が続き、
小さなミスで自分を責め、眠れない夜が続いた。
ある日、同僚に勧められて心療内科を受診した。
診断結果は「双極性障害」だった。
先生は穏やかに言った。
「もしかしたら、生い立ちの影響があるかもしれませんね」
その言葉に、私は心臓を掴まれたような感覚になった。
あの家庭での日々が、
今の自分の感情の波を作っているのかもしれない。
私は治療を受けながら、自分の心と向き合うことを始めた。
薬で症状を安定させつつ、カウンセリングで過去を語る。
初めて、あのときの恐怖を「言葉」に変えた。
涙を流しながら語るたびに、体の中にこびりついた痛みが少しずつ溶けていくようだった。
第10章 「理解すること」と「許すこと」は違う
治療を続けるうちに、私は心理学にも興味を持つようになった。
専門書を読み、心の構造を知ることが救いになった。
父もまた、幼少期に虐待を受けて育ったということを、母から聞いた。
母子家庭で、貧しく、愛情に飢えた少年だったらしい。
だからこそ、父は「怒る」ことでしか自分を保てなかったのかもしれない。
そう理解した瞬間、心の中に小さな変化が起きた。
「この人は、私を壊そうとしたわけじゃないのかもしれない」
それは許しではなかった。
ただ、“理解”に近いものだった。
理解することは、許すこととは違う。
でも、憎しみの中に留まり続けることの方が、私自身を傷つけている。
そう気づいたのはこの頃だった。
第11章 YouTubeが与えた転機——“許す”というテーマ
ある日、偶然見たYouTubeの動画で、
「公認心理師・橋本翔太」さんのチャンネルに出会った。
その中で彼はこう言っていた。
「過去の自分を救うのは、他の誰でもない。未来の自分です」
その言葉を聞いた瞬間、涙が止まらなかった。
私の中でずっと泣いていた“3歳の私”に、大人の私がようやく手を差し伸べられる気がした。
彼の話す「許し」の意味は、私がこれまで思っていたものと違った。
「許すとは、相手を肯定することではない。
ただ、自分がその怒りから解放されることだ。」
この考え方が、私の中の“鎖”を少しずつ緩めていった。
第12章 父との再会:沈黙の車中で
再会のきっかけは、母からの一本の電話だった。
「お父さんが、少し話したいって言ってるの」
胸の奥がざわついた。
何を話すつもりなのか。謝罪なのか、それとも言い訳なのか。
でも、避け続けても何も変わらない気がして、私は会うことを決めた。
久しぶりに見る父は、以前よりも小さく見えた。
白髪が増え、目の下には深いしわが刻まれていた。
それでも、私の体は反射的に緊張した。
あの声を聞くだけで、心臓が早くなる。
車の中は静まり返っていた。
父が何を言い出すのか、私はただ窓の外を見ていた。
しばらくして、父がぽつりと言った。
「ゆき、あの時はごめんな」
たった一言だった。
けれど、その瞬間、心の中の何かが崩れ落ちた。
涙が勝手に流れた。
第13章 「ゆき、あの時はごめんな」——30年分の涙
私は泣きながら言った。
「本当に、つらかったんだよ」
父はうつむきながら小さく頷いた。
その光景は、私が何度も頭の中で想像していた“謝罪の場面”とは違った。
もっと劇的なものを想像していた。
でも、実際はとても静かだった。
静かで、短くて、そして深かった。
父は言葉を探すようにして続けた。
「どうしても、あの頃はうまくやれなかったんだ」
その声は、あの頃の威圧的な声ではなく、弱さを含んでいた。
あの瞬間、私は理解した。
「父は変わった」のではなく、
「私が変われた」から、受け取れたのだと。
第14章 許すことの意味——自分を自由にする選択
私は、父を完全に許したわけではない。
今でも心のどこかで、「どうしてあんなことを」と思う自分がいる。
けれど、“許さないまま”では前に進めなかった。
許すことは、過去をなかったことにすることではない。
過去の出来事を、そのまま受け入れることだ。
そして、そこに縛られないこと。
「もう怒りを抱えたまま生きるのはやめよう」
そう決めた瞬間、心が少し軽くなった。
第15章 距離を保つという新しい関係性
父とは、今も頻繁に会うわけではない。
年に一度、年末に電話をする程度だ。
それで十分だと思っている。
和解したからといって、元のような親子関係に戻る必要はない。
むしろ、適切な距離を保つことで、穏やかでいられる。
私は父を“理解する”ことはできたが、
“同居する”ことはもうできない。
それが、私にとっての健全な関係だ。
第16章 母への気持ち、そして妹との絆
母との関係は、今でも複雑だ。
あの頃、母が助けてくれなかったことを完全に許すことはできない。
ただ、母もまた、弱い立場にいたことは理解している。
妹とは今でも連絡を取っている。
二人で幼いころの話をするとき、いつも最後は笑いに変わる。
「よく生き延びたね」と。
それが、私たち姉妹の“生存証明”のようなものだ。
第17章 私が親になって気づいたこと
子どもが生まれたとき、私は決意した。
「絶対に手をあげない」
小さな手を握った瞬間、
「この子は守られるべき存在だ」と心から思った。
父ができなかったことを、私はやりたい。
怒りではなく、対話で伝える。
それが、私の中で断ち切りたかった“暴力の連鎖”だ。
そして気づいた。
父は私を「怒り」でしか表現できなかったけれど、
それも一つの“愛の不器用な形”だったのかもしれない。
第18章 過去の自分への手紙
三歳の私へ。
あのとき、よく頑張ったね。
暗い押し入れで泣いていたあなたを、今の私は抱きしめたい。
泣いていい。
怖くていい。
あなたは悪くなかった。
あのときのあなたがいたから、今の私がいる。
本当にありがとう。
第19章 おわりに:同じように苦しむ人へ伝えたいこと
もし、今、この記事を読んでいるあなたが、
「親を許せない」「過去に縛られている」と感じているなら、
焦らなくていい。
許すことは義務じゃない。
無理に笑う必要もない。
ただ、自分の中で“整理すること”ができたら、それで十分だ。
そして、もし可能なら、専門家に話してほしい。
心理士でも、信頼できる友人でもいい。
語ることで、過去の自分が少しずつ救われていく。
私は26年かけて、ようやく“自由”という言葉の意味を知った。
それは、誰かに勝つことでも、忘れることでもない。
ただ、自分の人生を自分の手で取り戻すこと。
父を許すというより、
父の影に縛られていた“私自身”を解放することが、
本当の意味での「許し」だった。
結び
父と再会したあの日から、心の中の時計が少しずつ動き出した。
過去を変えることはできない。
でも、過去の意味は、自分で変えられる。
暗闇の押し入れで泣いていた私に、今ならこう言える。
「もう大丈夫。外は明るいよ」
【完全保存版】双極性障害と生きる私の記録はこちら↓
双極性障害でもフルタイム勤務を続けるための工夫はこちら↓
自立支援医療についての解説はこちら↓