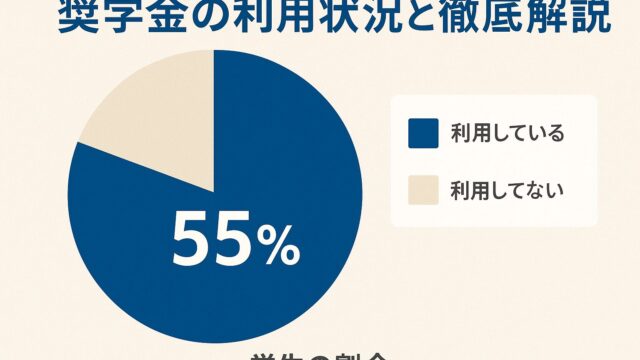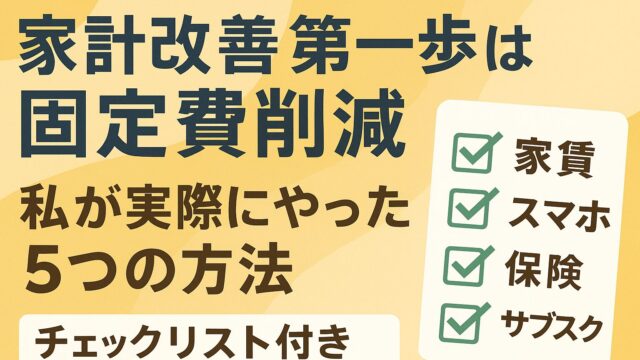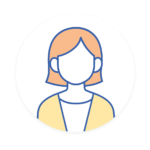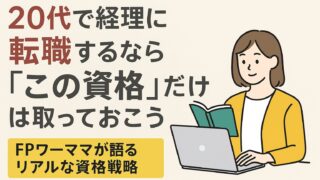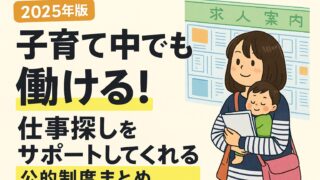都営住宅の収入基準とは?FPがやさしく解説【2025年版】

💬 はじめに
「家賃が重い…でも、引っ越す余裕もない。」
「メンタルの調子が安定せず、仕事も続けにくい。」
そんな中で目に留まったのが、都営住宅という選択肢。
今回は、実際に子育て中で双極性障害を抱えながらFPとしても活動する私が、
自分の経験を交えつつ、都営住宅の収入基準や申込のポイントをやさしく解説します。
🪴 きっかけは「子育て支援のパンフレット」から
都営住宅を知ったのは、区役所で配られていた「子育て支援のパンフレット」がきっかけでした。
当時の私は双極性障害の症状が重く、退職して専業主婦になっていました。
夫は大学院生で、世帯収入は年間100万円ほど。
「子育てをしながら生活を支えるには、もう少し安心できる住まいがほしい」と思っていた頃でした。
都営住宅の欄を見て、「こういう制度があるんだ」と初めて知ったのです。
💻 申込は意外と簡単。公的書類を出すだけ
「審査って大変そう」「書類が面倒なのでは?」
そう思っている方も多いと思います。
でも実際には、申込はとてもシンプルでした。
申込はインターネットからできて、必要なのは公的な証明書(課税証明書など)の提出だけ。
自分で特別な書類を作成する必要はありません。
制度はしっかりしているけれど、申込自体はとても簡単。
「公営住宅=手続きが難しい」というイメージが変わりました。
💰 都営住宅の「収入基準」は意外とゆるい?
FPとしてデータを見ると、都営住宅の「収入基準」は意外と柔軟です。
都営住宅でいう「所得」は、確定申告書で使う「課税所得」とは少し違います。
実際には、さまざまな控除を考慮したうえで計算されるため、結果的に低めになることが多いんです。
つまり、「確定申告では所得が高く見えても、都営住宅の基準では通る可能性がある」ケースも。
🟢 例えば、医療費控除・社会保険料控除・扶養控除などをしっかり反映させることで、
実際の“都営住宅上の所得”は数十万円単位で変わることがあります。
✍️ 実際に行った「所得控除アップの工夫」
我が家の場合、夫が学生で私は専業主婦。
世帯収入は少なかったのですが、念のため控除を最大限に活用しました。
具体的には、
- 学生時代の「年金未納分(学生納付特例)」を追納
- ふるさと納税を活用
これだけでも、所得控除額が増えて、基準内に収まるケースがあります。
FPとしても、節税や申込資格を考える上で「控除」はとても重要だと感じます。
📊 都営住宅の収入基準目安(2025年時点)
| 世帯区分 | 月額所得の目安 | 対象例 |
|---|---|---|
| 一般世帯 | 約15.8万円以下 | 夫婦・子1人など |
| 特別枠(高齢者・障害者・母子家庭など) | 約21.4万円以下 | 障害年金受給・ひとり親など |
(出典:東京都住宅供給公社)
💡つまり、「障害年金を受けている世帯」や「パート収入のみの世帯」は、
特別枠で申込できるチャンスが広がるということです。
🧾 どんな収入が対象になるの?
「障害年金って収入に入るの?」「パート収入はどう?」
という質問をよく受けます。
FPとしての答えはシンプルです。
✅ 非課税の収入以外は、すべて収入です。
つまり、年金・パート・給与・ボーナスなどはすべてカウント対象。
ただし、生活保護費・給付金など非課税扱いのものは除外されます。
「何が対象になるか」は、公的サイトでも一覧が出ています👇
👉 東京都住宅供給公社:収入基準の考え方(PDF)
🌱 「収入が下がっても家賃も下がる」安心感
都営住宅の大きな特徴は、家賃が収入に応じて決まること。
つまり、収入が下がれば家賃も下がります。
この仕組みが、私にとっては本当に大きな支えでした。
「もし働けなくなっても、家賃が上がらない」
この安心感は、何にも代えがたい。
収入が増えたら家賃が上がる、
減ったら下がる。
そんな「柔軟な制度」が、メンタル的にも家計的にも心強いです。
💬 当選を待つ人の気持ち
都営住宅の申込者の多くは、家計や健康の事情を抱えています。
中には、障害年金で生活している人、シングルマザー、低収入の学生世帯もいます。
みんな、「あたるといいな」と願いながら申込を続けている。
私もそのひとりでした。
「制度を使えるものは使う」
そういう気持ちで、常にアンテナを張っていました。
都営住宅は“恥ずかしい制度”でも“特別な制度”でもありません。
生きていくうえで必要な、「安心の選択肢」のひとつです。
📘 FPが見た「誤解されがちなポイント」
意外と多いのが、「自分は収入があるから無理だ」と最初からあきらめてしまうケース。
でも、FP目線で見るとそれはもったいない誤解です。
なぜなら、
都営住宅の「所得」は一般的な課税所得よりも低く計算されることが多く、
控除を考慮すると申込できる人が多いからです。
💬「確定申告上の所得ではダメでも、都営住宅上の所得ならOK」
というケースが本当にたくさんあります。
だからこそ、
「どうせ通らない」と思う前に、一度計算してみてほしい。
PDFの計算表を見ながら、あなたの実際の数字で確かめる価値があります。
🏡 都営住宅がくれた“生活の安定”
家賃(固定費)が安いというのは、何にも代えがたい安心感です。
それは単に「お金の話」ではなく、心の安定にもつながります。
双極性障害を抱えながら生きていく中で、
「住まいの不安がない」というのは、想像以上に大きい。
病気で働けない時期があっても、
家賃の心配がないだけで、次の一歩を踏み出す余力が生まれる。
これは“暮らしのセーフティネット”であり、
“心を支える制度”でもあるのです。
🌿 まとめ:あきらめずに、制度を味方に
都営住宅の収入基準は、数字だけを見ると難しそうですが、
実際には“生活に寄り添う仕組み”になっています。
- 所得控除を活用すれば、基準内に入ることが多い
- 障害者や低所得世帯は特別枠がある
- 家賃は収入に応じて柔軟に変動する
だから、最初から「無理」と決めつけず、
まずは自分の収入を落ち着いて確認してみてください。
都営住宅は、誰かを助けるために存在する制度です。
あなたがその対象であっても、何もおかしくありません。
💬 最後に、これから申し込む方へ
「家賃が安い=生活が安定する=心も落ち着く」
お金のゆとりは、心のゆとりに変わります。
一度、制度を見直してみてください。
都営住宅は、“頑張り続けるあなた”を少し楽にしてくれる選択肢です。
🕊 心と暮らしの手帖より
FPとして、そして一人の生活者として、
「制度を知ることは、自分を守ること」だと実感しています。
このブログが、あなたの安心の一歩になれば嬉しいです。