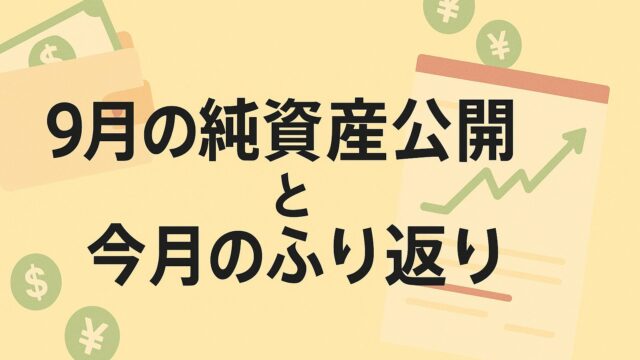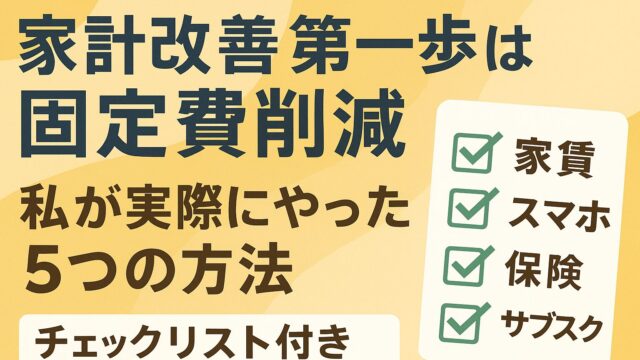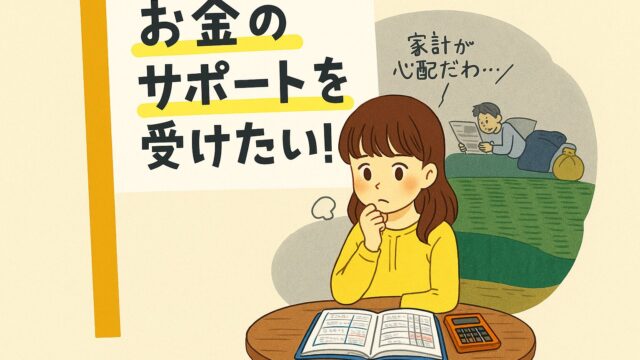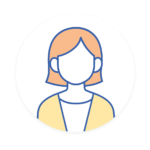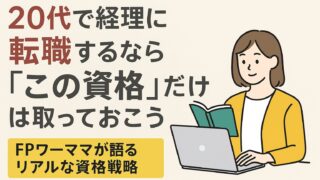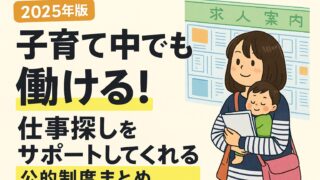【知らないと損】2025年版 児童手当の拡充と最大限活用する方法

この記事でわかること
- 2024年10月以降に改正された児童手当制度の最新ポイント
- 支給対象・年齢・所得制限の変化
- 支給額と多子加算(第3子以降)のしくみ
- 支給スケジュール・申請方法・注意点
- 児童手当を「貯蓄・教育費・家計補助」に賢く使う方法
- ケースシミュレーション(共働き・シングル・多子家庭など)
- よくある誤解・Q&A
- 今日からできるチェックリスト
1. はじめに ― “知らないと損” という理由
子育て中の家庭にとって、公的支援制度はまさに「使える権利」。
しかし、その制度が変わることや、改正ポイントを把握できていないことで、本来受け取れるはずの金額を逃している家庭が少なくありません。
とりわけ、児童手当は改正によって 支給対象年齢の拡大・所得制限の撤廃・多子加算強化・支給回数の増加 といった大幅な変化を迎えています。これらを知らずにいたら、年間で数万円〜数十万円、場合によってはそれ以上の支援を失ってしまう可能性があります。
本記事では、FP(ファイナンシャルプランナー)の視点から、改正内容を丁寧に紐解き、「どう使えば一番得なのか」を示す実践的なガイドをお届けします。
制度をただ受け取るのではなく、“育てるお金” に変えるヒントも盛り込みましたので、ぜひ最後までお付き合いください。
2. 児童手当制度の改正ポイント
まず最初に、改正前後の制度の違いを押さえましょう。これがこの記事の基盤となります。
2-1. 支給対象年齢の拡大
従来、児童手当の支給対象は「中学生年代まで」、すなわち「15歳到達後の最初の3月31日まで」の子どもが対象でした。
このため、高校を卒業する18歳や、それ以上の年齢の子どもには支給されず、家庭の負担になっていました。
しかし、2024年10月の法改正後、 支給対象年齢が「高校生年代」、つまり 18歳到達後の最初の3月31日まで に拡大されました。 広島市ファンクション+4横浜市公式サイト+4北区役所サイト+4
この改正により、高校生を育てる家庭も児童手当を受け取ることが可能になります。
ただし、「支給対象になるからといって自動的に受け取れるわけではない」点に注意が必要です。後半で申請条件・手続きの点をご説明します。
2-2. 所得制限の撤廃
児童手当には、これまで所得制限が設けられており、一定以上の所得がある世帯は支給対象外、または“特例給付”という低額給付になるケースもありました。
ですが、改正後は 所得制限が撤廃され、所得に関わらずすべての受給対象世帯が正規支給を受けられるようになります。 北区役所サイト+6政府の窓口+6CFA Japan+6
この変更により、これまでは支給除外だった高所得世帯にも恩恵が及ぶようになります。
ただし、注意点として、所得が高い方は他の税制・控除制度との兼ね合いで、実質的な税負担が増える可能性もあります。後ほど高所得世帯視点での注意点も扱います。
2-3. 支給金額・多子加算の強化
最も注目すべき改正の一つが 第3子以降(多子加算) の支給額強化です。
改正前後の支給額比較を以下の表にまとめます(代表例)。
| 年齢区分/子の順番 | 改正前の支給額 | 改正後の支給額 |
|---|---|---|
| 0~2歳(第1/第2子) | 15,000円 | 15,000円 |
| 0~2歳(第3子以降) | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~高校卒業(第1/第2子) | 10,000円 | 10,000円 |
| 3歳~高校卒業(第3子以降) | 15,000円 | 30,000円 |
| 中学生(第1/第2子) | 10,000円 | 10,000円 |
| 中学生(第3子以降) | 15,000円 | 30,000円 |
(出典:こども家庭庁「児童手当の案内」 CFA Japan、横浜市改正案内 横浜市公式サイト、各自治体サイト)
つまり、改正後は 第3子以降は年齢に関わらず一律30,000円/月 が基本線になります。 CFA Japan+4豊中市公式ウェブサイト+4横浜市公式サイト+4
また、多子加算の “子どもの数え方(カウント方法)” も見直されました。従来は18歳到達後は対象外とされていた子も、22歳到達後の年度末まで はカウント対象になる制度が導入されます。 広島市ファンクション+4横浜市公式サイト+4大田区公式サイト+4
この仕組みにより、高校卒業後進学中の子どもがいる家庭にも加算対象になる可能性があります。ただし、その扱いには「監護相当・生計費負担」の確認書類提出など、自治体による手続きが必要なケースがあります。 北区役所サイト+3大田区公式サイト+3大阪市公式ウェブサイト+3
2-4. 支給回数・支給タイミングの変更
改正前は 年3回支給(2月・6月・10月)、それぞれ前月までの4か月分をまとめて支給する制度でした。
改正後は 年6回支給 に変更され、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月) に支給されます。支給分は 前月までの2か月分 ずつ。 CFA Japan+4政府の窓口+4CFA Japan+4
これにより、支給を待つ期間が短くなり、家庭の資金繰りが楽になる効果が見込めます。
また、制度改正後の初回支給日は 令和6年12月(10月分・11月分を含む) と設定されており、12月5日支給となる自治体もあります。 大阪市公式ウェブサイト+2国分寺市公式ウェブサイト+2
3. 支給対象・申請条件の実務チェック
ここからは、「自分が制度の恩恵を受けられるか」を見極めるための具体的な要件や注意点を整理します。
3-1. 誰が請求できるか・対象となる児童
- 支給対象児童は 0歳~18歳到達後の最初の3月31日まで の子ども(高校生年代まで)です。 広島市ファンクション+5CFA Japan+5CFA Japan+5
- ただし、第3子以降の算定対象としては、18歳を超えた子どもも 22歳到達後の最初の3月31日まで カウント対象になる制度改正がなされています(ただし支給対象とは異なります) CFA Japan+4大田区公式サイト+4大阪市公式ウェブサイト+4
- 父母等のうち、所得が高い方 が原則として支給請求者となります。従来からこのルールは維持されており、共働き家庭ではどちらが請求者になるか確認が必要です。 相模原市公式サイト+2CFA Japan+2
- 離婚・別居・養育責任の分担など特殊なケースでは、請求者や受給可否に注意が必要です。子どもと同居している親が請求するケースが多いですが、自治体の判定に委ねられる場合もあります。 京都市+4CFA Japan+4CFA Japan+4
- 施設入所中の子どもは、施設の設置者が受給者になるケースもあります。 CFA Japan+1
3-2. 申請手順・現況届・更新
- 新たに対象となった家庭・条件が変わった家庭は、認定請求書 を市区町村に提出する必要があります。改正後の拡充対象者は、この申請によって 2024年10月分から遡及支給を受けられる可能性が設けられています(申請期限あり) 京都市+6CFA Japan+6京都市+6
- 各自治体では、令和7年3月31日 を申請猶予期間の期限として定めており、この期間を過ぎると遡及支給ができません。 国分寺市公式ウェブサイト+3京都市+3CFA Japan+3
- 既存受給者であっても、支給額変更・多子加算対象追加などがあれば、額改定請求 や 監護相当・生計費負担の確認書 の提出が必要な場合があります。特に大学生年代になった子どもを多子加算に含めたい場合は、この手続きが不可欠です。 豊中市公式ウェブサイト+4大田区公式サイト+4大阪市公式ウェブサイト+4
- 毎年の 現況届(現状届出) の提出は必須です。多くの自治体で 6月提出 が定められており、未提出の場合はその年以降の受給が停止されるリスクがあります。 政府の窓口+3横浜市公式サイト+3横浜市公式サイト+3
- 転居・住所変更・世帯構成変化がある場合は、早めに自治体に届け出る必要があります。
3-3. 受給停止・過払い・返還リスク
- 所得の急激な上昇、扶養状況の変更などにより、その年の受給額が見直され、過払いが発生することがあります。その場合、返還請求が来るケースもあります。
- 虚偽申告や事実と異なる申請があった場合、返還義務が発生します。
- 多子加算の算定対象となっていた子どもが大学卒業などで条件から外れる場合、請求届けを行わないと加算が外されることがあります。 相模原市公式サイト+3大阪市公式ウェブサイト+3大田区公式サイト+3
- 支給が停止されるケース:現況届未提出、高校卒業後の子、施設収容中の子、別居・監護状況の変更など。
4. “もらう”だけじゃもったいない! 賢い使い道と運用法
制度を理解したら、次はその“お金”をどう扱うか。受け取っただけで終わらせず、家庭の資産につなげる考え方を取り入れましょう。
4-1. 教育費資金化のアプローチ
- 毎月定額で 積立投資 に回す
児童手当相当額を、つみたてNISA・学資保険・定期預金・ジュニアNISAなどへ振り向け、将来教育費に育てる戦略が効果的です。 - 先取り貯蓄として使う
受給額が確定したら、すぐに教育費用口座に自動振替設定しておくことで“使ってしまうリスク”を防ぎます。 - 奨学金返済や進学準備に充てる
子どもが高校・大学に進む際の準備金に充当すると、家計の負担が軽くなります。
4-2. 家計補填として使うなら優先順位を意識
- 変動費の補填(光熱費・通信費・食費など)
- 不定期出費(修繕費・医療費など)
- 貯蓄・予備費としてストック
- 必要ならローンの繰上返済に充てて利息負担を軽くする
ただし「手当を使い切る」発想ではなく、「使いつつも将来を見据えた運用」を心がけると差が出ます。
4-3. 節税・資産形成との接続
- 児童手当は課税所得に含まれず、非課税所得扱いとなります(つまり、この受給自体で所得税が増えることはありません) CFA Japan
- ただし高所得層は、扶養控除・配偶者控除など他制度との兼ね合いで実質税負担が変動する可能性があります。特に所得制限撤廃後は、この点を意識すべきです。 apart.familycorporation.co.jp
- 受給した手当を、iDeCo・つみたてNISAなどの非課税制度に振り向けると、複利効果によって資産拡大も期待できます
- 他の子育て支援制度(奨学金給付金・補助金・助成金)との併用可否をシミュレーションして最大活用を図る
5. ケースシミュレーション集
具体例を見ることで、あなたの家庭で受給可能な額や活用イメージをつかみやすくなります。
ケース A:共働き家庭(子ども2人)
- 夫婦年収合計:600万円
- 子ども:6歳、3歳
支給額計算例:
| 子ども | 年齢 | 支給額(月額) | 年間支給額 |
|---|---|---|---|
| 子1(6歳) | 10,000円 | 120,000円 | |
| 子2(3歳) | 15,000円 | 180,000円 | |
| 合計 | — | — | 300,000円 |
仮にこの全額を毎年「教育費積立」に回したとすると、10年で 300,000円 × 10年 = 3,000,000円分の資金を得られる可能性があります(利息・運用益除く)。
ケース B:シングルマザー家庭(子ども3人)
- 年収:300万円
- 子ども:16歳・14歳・8歳
改正後の多子加算の影響が強く出る家庭です。
支給額例:
| 子ども | 年齢 | 支給額(月額) |
|---|---|---|
| 16歳 | 10,000円 | |
| 14歳(第2子) | 10,000円 | |
| 8歳(第3子) | 30,000円 | |
| 合計月額 | — | 50,000円 |
年間支給額は 600,000円 に達します。これは家計にとってかなり大きなサポートになります。
他の想定パターン
- 高所得世帯(年収1,200万円、子ども2人)
→ 所得制限撤廃により、これまでは支給除外だった世帯も受給対象に - 大学生進学中の子どもがいる家庭
→ 多子加算のカウント対象になるかどうかが、加算額を決める鍵
6. よくある誤解とQ&A
児童手当は一見シンプルな制度に見えますが、実際には多くの“勘違いポイント”があります。
ここでは、よくある質問をFP目線でわかりやすく解説します。
Q1. 所得制限が撤廃されたら、誰でも自動的にもらえるの?
→ いいえ。自動的には支給されません。
新たに支給対象となった世帯(高校生のいる家庭、高所得世帯など)は、必ず認定請求書を提出する必要があります。
申請をしていないと「対象でも受け取れない」ため要注意です。
Q2. 過去に所得制限で除外されていたが、申請していなかった。今からでも遡ってもらえる?
→ はい、条件付きで可能です。
2024年10月に制度改正が施行されたため、令和7年3月31日まで に申請すれば、2024年10月分からの遡及支給を受けられます。
期限を過ぎると、申請月の翌月分からしか受け取れません。
Q3. 子どもが海外留学中だけど、児童手当はもらえる?
→ 原則として 国内居住が条件 ですが、教育目的での短期留学など一定の条件を満たせば支給対象になります。
「教育目的」「国内に生活基盤がある」などを証明できればOKです。
Q4. 共働き夫婦ではどちらが申請者?
→ 原則は 所得が高い方(生計中心者) です。
ただし、実際に子どもと同居している親が申請者になるケースもあります。
別居・転勤などで複雑な場合は、住民票と扶養関係の確認を自治体が行います。
Q5. 離婚・再婚後も受け取れる?
→ 受け取れますが、監護している親(子と同居している側) が申請者となります。
再婚相手の子どもを養育している場合も、戸籍上の続柄と生計関係で判断されます。
Q6. 子どもが施設に入っている場合はどうなる?
→ 児童手当は 養育者ではなく施設の設置者や里親 に支給されます。
家庭での受給は停止されるので注意してください。
Q7. 支給日はいつ?
→ 改正後は 偶数月の10日頃(自治体により前後) に支給されます。
例えば、4月支給分は「2月・3月分」、6月支給分は「4月・5月分」というように2か月分まとめて支給されます。
Q8. 所得証明書を出し忘れたらどうなる?
→ 現況届や所得確認書類を提出しないと、翌年度から支給が一時停止される可能性があります。
再開には手続きが必要で、遡及されない場合もあるため必ず期限内提出を。
Q9. 子どもが高校を卒業した後も支給される?
→ 支給対象は「18歳到達後の3月31日まで」なので、高校卒業の翌月以降は支給対象外です。
Q10. 第3子以降の数え方がわからない
→ 改正後は、高校生や大学生年代の子どもも加算カウント対象になります。
ただし、実際に支給されるのは18歳までなので、「加算対象」「支給対象」を分けて考えるのがポイントです。
7. 今日からできるチェックリスト
受給漏れや申請ミスを防ぐために、今すぐ確認しておきましょう。
| チェック項目 | 内容 | 完了 |
|---|---|---|
| ① 制度改正の概要を理解した | 支給年齢拡大・所得制限撤廃・多子加算を確認 | ☐ |
| ② 自治体サイトで詳細を確認 | 例:横浜市・大阪市・東京都大田区など | ☐ |
| ③ 新しく対象になった子どもがいないか確認 | 高校生・第3子など | ☐ |
| ④ 認定請求書を提出 | 令和7年3月31日までに必須 | ☐ |
| ⑤ 現況届を期限内に提出 | 6月が基本。未提出は停止リスクあり | ☐ |
| ⑥ 支給額・支給日を家計簿に記録 | 偶数月支給をスケジュール管理 | ☐ |
| ⑦ 他制度との併用を検討 | 例:児童育成手当・教育費支援給付金など | ☐ |
| ⑧ 手当の使い道を決める | 教育費・積立・投資など | ☐ |
💡 FPアドバイス
手当を“臨時収入”と考えるのではなく、“将来の教育費積立”として口座分けしておくと◎。
家計の安定化にも貯蓄にもつながります。
8. 制度をさらに賢く使う裏ワザ
児童手当は単体でも十分ありがたい制度ですが、他の支援制度と組み合わせると相乗効果が生まれます。
8-1. 教育費支援制度と併用
- 高校授業料無償化(高等学校等就学支援金)
→ 世帯年収約910万円未満で対象。児童手当とダブルでもらえます。 - 奨学金給付型制度(JASSO)
→ 高校生・大学生向けに年数十万円支援される給付型奨学金。 - 地方自治体の子育て助成金
→ 横浜市・大阪市などでは独自の「子育て世帯応援給付金」あり。
📊 併用効果例(共働き・子3人家庭)
| 制度名 | 年間支給額 | 合計受給額(年間) |
|---|---|---|
| 児童手当(第3子加算) | 約60万円 | |
| 高校授業料無償化 | 約12万円 | |
| 児童育成手当 | 約10万円 | 計82万円支援可能! |
8-2. 節税制度との組み合わせ
- ふるさと納税:手当で得た金額を寄付に回せば実質2,000円で返礼品+税控除。
- iDeCo・NISA:児童手当を原資に非課税運用で資産形成。
- 医療費控除・高額療養費制度:手当と組み合わせて医療費負担を軽減。
8-3. 家計改善にも活用できる
児童手当は非課税収入なので、
- 緊急予備費
- 教育資金口座
- 投資資金
など、目的別に分けると家計が劇的に安定します。
FPとしておすすめなのは、
「児童手当の自動積立」設定。
給与口座に振り込まれたら即、別口座に移すだけで“使わず貯まる”仕組みが完成します。
9. まとめ・結論
最後に、この記事の要点を3行でまとめましょう。
✅ 児童手当は2024年10月から大幅改正
- 高校生まで支給対象拡大
- 所得制限撤廃で全世帯対象
- 第3子以降は月3万円の大幅加算
✅ 申請しないと受け取れない!
- 自動支給ではなく「認定請求書」の提出が必要
- 令和7年3月31日までが遡及支給の期限
✅ 使い方次第で“将来の資産”に変わる!
- 受給金を教育費・積立投資に回せば、10年で数百万円の差
- 他の制度と併用すれば年間80万円以上の支援も可能
FPのひとことアドバイス💬
「制度は“知っている人だけが得をする”もの。
申請はあなたの権利です。ためらわず、しっかり使いこなしましょう。」
10. 参考資料・出典
- こども家庭庁「児童手当」案内ページ(cfa.go.jp)
- 政府広報オンライン「児童手当の制度改正」(gov-online.go.jp)
- 横浜市・大阪市・大田区・京都市公式サイト
- 日本政策金融公庫・JASSO 奨学金制度
- 金融庁「つみたてNISA」「iDeCo」公式情報